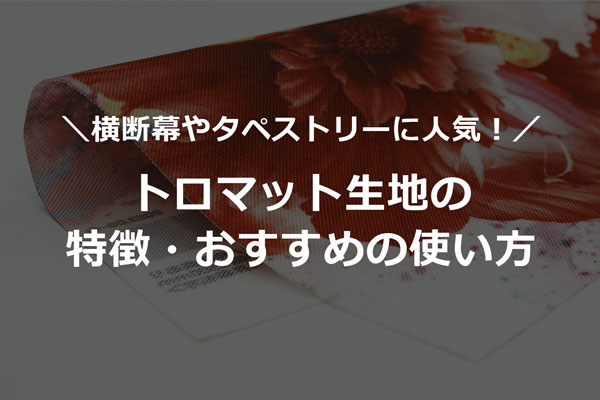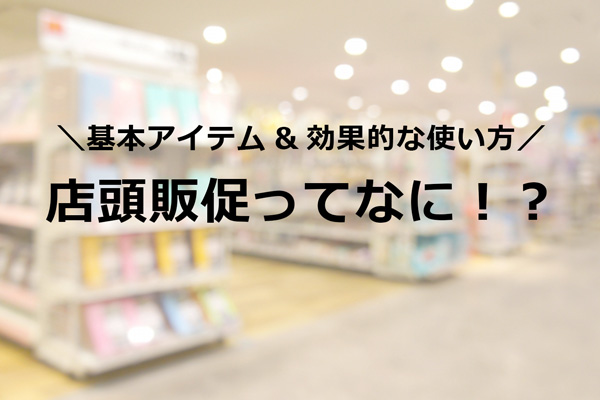
店頭販促は店舗を運営するうえで欠かせません。
飲食店であれば新メニューのポスターを貼り、ショップならセール時にのぼり旗を設置するなど、店頭販促には多くのアイテムがあります。
しかし、どのアイテムを使うか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。
店頭販促に使うアイテムを間違えれば効果が出ないだけでなく、店舗のイメージがマイナスになることもあります。
一方で店頭販促を効果的に行えば、多くの顧客を誘導し、購買意欲を向上させて売上に繋げることができるでしょう。
本記事では、店頭販促の基本的なアイテムや成功させるためのポイント、注意点などをご紹介します。
これから店頭販促をしたいと考えている方、店頭販促をしているけど思ったような効果が出ないという方もぜひ参考にしてみてください。
それではみていきましょう。
店頭販促とは?
店頭販促とは店頭で行われる販売促進の手法のことです。
具体的なツールは冒頭でお伝えしたようなポスターやのぼり旗のほか、チラシやパネルなどさまざまで、とくに決まりはありません。
自分の店舗に合ったツールを使って商品やサービスをプロモーションし、顧客の来店や購買意欲を上げて、最終的には購入に繋がることを目的とします。
店頭販促は店舗の運営では欠かせない活動といえますが、なぜ必要なのでしょうか。
具体的にみていきましょう。

集客をアップさせるため
1つ目は集客をアップさせるためです。
店舗にいくら良い商品やサービスがあっても、集客がなければ売上に繋がりません。
まずは店舗を知ってもらうために、商品やサービスのプロモーションをしましょう。
そのときは、初めてでも入店しやすいような雰囲気づくりを心掛けると効果的です。
例えば、店舗の中が見にくい、価格帯が分からないといった場合は入店を躊躇してしまう方もいます。
店舗の中は見やすくディスプレイし、店頭販促で商品やサービスを明確に表示すれば集客のアップも期待できます。
売上をアップさせるため
2つ目は売上をアップさせるためです。
店頭販促では購買意欲の向上が期待できます。
商品の情報やサービスの内容はもちろんですが、セールやキャンペーンのお得な情報や限定品の発売など、顧客にとってメリットになる情報を伝えましょう。
例えば、スーパーで良くみられる手法で下記のようなものがあります。
「1つなら〇〇円、3つまとめて購入すれば〇〇円!」
自分の欲しい商品はもちろん、少し気になっている程度でも、明らかにお得だと思わず買ってしまうことがありませんか?
これは、いわゆる「まとめ買い」を促す店頭販促ですね。
「まとめ買い」になれば、当然ながら客単価が上がります。
集客アップ>購買意欲アップ>客単価アップ
このような好循環を作り出すことができれば、安定した店舗運営ができているといえるでしょう。
では次に、店頭販促の具体的なアイテムをみていきましょう。

1.のぼり旗
1つ目はのぼり旗です。
のぼり旗はポンジと呼ばれる薄手の生地に印刷をして、ポールに括りつけて使われます。
飲食店やスーパーなど身近で使われているので、誰でも見たことがありますよね。
一般的に使われるサイズは横600mm、縦1800mmですが、大小さまざまなサイズで作ることが可能です。
設置は柱に取り付けたり、スタンドを使えば自立させることもできます。
のぼり旗は価格が安く、手軽に設置できる上に販促効果が高いので、初心者でも導入しやすい店頭販促でしょう。

2.ポスター
2つ目はポスターです。
ポスターは壁や窓に手軽に貼ることができる店頭販促です。
ポスターのサイズは、一般的にA2やA1、B1などの規格サイズが多くみられます。
制作枚数が少量の場合はインクジェット印刷を利用することで、コストを抑えることができるでしょう。
また、頻繁に入れ替えをしたいときは、ポスター専用のフレームを導入すると便利です。

入れ替えが簡単な専用フレーム「ポスターグリップ®」
3.バナースタンド
3つ目はバナースタンドです。
バナースタンドとは、バナーと呼ばれる印刷した生地を自立させて使う什器のことです。
バナースタンドにはさまざまな種類があります。
軽量で低価格のXバナーや、設置が便利なロールアップタイプ、バックボードとしても使える大型タイプもあるので用途によって選びましょう。
什器は繰り返し使うことができるので、バナーを入れ替えれば何度でも使えます。
多くのバナースタンドは一人でも簡単にバナーを取り付けられる構造になっているので、設置も簡単にできますよ。

Xバナースタンドの使用例
4.タペストリー
4つ目はタペストリーです。
タペストリーとは、印刷した生地を壁掛けや天吊りで設置して使うもので、店頭販促のほかにインテリア装飾でも使われています。
タペストリーの生地には様々な種類があります。
近年では環境問題に配慮して、廃棄回収されたPETボトルから作られたサステナブルな生地の「PETボトルクロス」も話題になっています。
タペストリーは生地によって雰囲気がガラッと変わるので、店舗のイメージに合わせたものを選ぶと良いでしょう。
できれば、印刷前にサンプルなどで生地の質感を確認しておくと安心です。

ターポリン生地を使用したタペストリー
5.デジタルサイネージ
5つ目はデジタルサイネージです。
デジタルサイネージとは、モニターなどのデジタル機器を看板代わりとして使い、あらゆる機能もデジタル化した販促方法です。
比較的新しい店頭販促ですが、駅の構内やアパレルショップなどで見かけることも増えてきました。
入れ替え作業は映し出すデータを変更するだけなので、印刷代や取り付け費が発生しません。
初期費用は高額ですが「新商品が頻繁に出る」「入れ替えの度に専門業者に設置を依頼している」といったケースであれば、長期的に考えるとコスト削減になることもあります。
「パソコンが苦手なので難しそう…」と敬遠する方もいますが、最近ではスマホやタブレットでも簡単に操作できるコンテンツも増えています。

デジタルサイネージの参考画像
6.ノベルティ
6つ目はノベルティです。
ノベルティとは、店舗が商品やサービスの認知度を高めるため、グッズなどを無料で配布することです。
ノベルティには、認知度や親近感を向上させる狙いがあるため、日常的に使うボールペンやタオル、エコバッグなどの雑貨が多くみられます。
人気のあるノベルティにすれば、来店のきっかけや購入意欲の向上も期待できるでしょう。
7.パネル・等身大パネル・POP
7つ目はパネル・等身大パネル・POPです。
パネル・等身大パネル・POPには基本的にボード素材が使われます。
ボード素材にはいくつかありますが、代表的な素材はスチレンボードです。
スチレンボードとはポリスチレンを主原料とした発泡板です。
カッターなどで簡単に切れるので、四角のほかにも人の形や吹き出し、星形など好きな形に切って使うことができます。
スチレンボードは100均ショップでも購入できるので、サイズが小さければDIYで作ることもできるでしょう。

スチレンボードで製作した等身大パネル
以上が店頭販促の基本アイテムです。
続いて、店頭販促ポイントを成功させるポイントをみていきましょう。
商品をわかりやすくディスプレイする
1つ目は、商品をわかりやすくディスプレイすることです。
陳列が見にくく、欲しい商品が見つからない場合は、探すのが面倒になって退店してしまうこともあります。
どこに何があるのか、誰がみてもわかりやすいディスプレイにすることで、スムーズな購入へと繋げることができるでしょう。
シリーズものやサイズ違いなどがあれば、関連商品として紹介しても効果的ですね。
明確なデザイン
2つ目は明確なデザインです。
店頭販促ではまず足を止めてもらい、店舗に興味を持ってもらうことが大切です。
そのためには、パッと見てわかりやすい明確なデザインにすると効果的です。
よくある失敗例では、商品の良さを伝えたいあまり、情報を詰め込みすぎたデザインにしてしまうことです。
情報量が多すぎると読みにくいだけでなく、購入の意思決定の質が下がる傾向にあります。
多くの情報を伝えたい場合は、パンフレットなど別の媒体で製作するようにして、店頭販促では明確なデザインにしましょう。
顧客にとってのメリットを連動
3つ目は顧客にとってのメリットを連動することです。
例えば、キャラクターグッズを販売する株式会社キディランドの事例をご紹介します。
キディランドの2店舗(原宿店、大阪店)で、ゲームキャラクター・カービィの“KIRBY’S PUPUPU MARKET サマーキャンペーン 2023”が開催されました。
キャンペーン中には新商品のエコバッグやトートバッグが発売されるほか、対象商品を2000円以上購入するとノベルティのオリジナルアクリルフィギュアがもらえるというものです。
アクリルフィギュアは全5種類のランダム封入。
カービィは1992年の誕生以来、根強い人気のあるキャラクターで、ファンのなかにはすべてのデザインを集める人もいるほど。
新商品をいち早く購入できるだけでなく、ノベルティの特典まであるとなれば購入意欲も向上しますね。
【原宿店・梅田店】
8/10(木)~PUPUPU MARKET2店舗にて「KIRBY’S PUPUPU MARKET サマーキャンペーン 2023」がスタート
効果測定をする
最後は効果測定をすることです。
前項で、店頭販促にはさまざまなアイテムがあることをお伝えしました。
店舗によって効果の出る店頭販促は異なります。
使ったアイテムごとに売上を管理しておくと、自分の店舗にはどの店舗販促が合っているのか分かるようになります。
その際、使用した場所や期間、デザインなどの情報も管理しておくことで、成功パターンを導きだすことができるでしょう。
以上が店頭販促のポイントになります。
つぎに店頭販促の注意点をみていきましょう。
顧客の導線に沿った配置にする
1つ目は顧客の導線に沿った配置にすることです。
顧客が店舗を見つけて、どこに視線を向けて入店するのか、どのような順路で店内を歩くのかをしっかりイメージして配置します。
スタッフ目線ではどうしても押し売りになりがちなので、顧客の立場になって考えてみましょう。
そして、購入に至るまでは必ずストーリーがあります。
全体的なストーリーをイメージして、要所要所で店頭販促を設置すると効果的です。
環境に合ったアイテムを使う
2つ目は環境に合ったアイテムを使うことです。
例えば、バナースタンドを設置するとしましょう。
軽量タイプは持ち運びが簡単で価格も安いメリットがありますが、
万が一接触すると、什器ごと倒れてしまうことがあります。
什器が倒れると破損するだけでなく、最悪の場合は通行人にケガを負わせてしまう可能性もあるでしょう。
もし人通りの多い場所でバナースタンドを設置するなら、什器が安定する注水タンク付きが安心です。
このように、店頭販促は周囲の環境に合ったアイテムを選ぶことが大切です。
情報の更新を忘れない
3つ目は情報の更新を忘れないことです。
例えば、新型が発売されているのに、旧型に「新商品」のPOPが付いたままになっていたらどうでしょうか。
顧客は混乱するだけでなく、店舗の管理体制にも疑問を持ちかねません。
購入に導くためには、店舗と顧客との信頼関係が何より必要です。
店頭販促の情報は最新になっているか、定期的に確認しましょう。
以上が店頭販促の注意点です。
最後に店頭販促以外に効果のあるものをご紹介します。
店頭販促以外に効果のあるもの
これまでもご説明してきたとおり、店頭販促は顧客の来店、購入意欲の向上のために効果的なものです。
しかし、店頭販促には導入費や設置場所の確保が必要となるほか、なにより店舗近辺に顧客がいないと訴求できないデメリットもあります。
このデメリットを解消するために、近年増加しているのがSNSです。
SNSは基本的に無料で始めることができ、インターネット上で誰でも見ることできます。
店舗に設置場所を用意する必要もありません。
そして、SNSの最大の魅力は「拡散効果」です。
SNS上で「いいね」や「リプライ」などのアクションが起きれば、多くの人に情報が拡散されることが期待できます。
とくに若年層をターゲットにしている店舗では、SNSを有効に活用することで高い販促効果が見込めるでしょう。
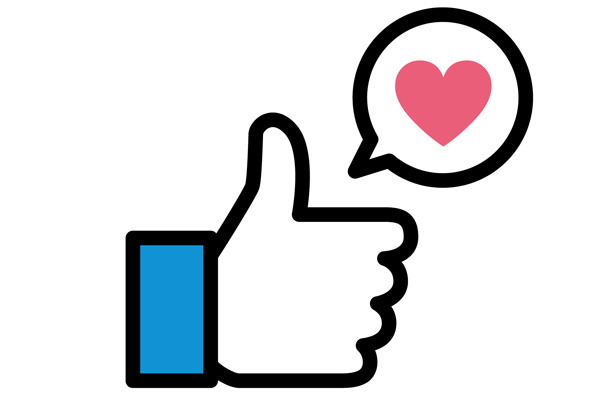
まとめ
いかがでしたでしょうか。
店頭販促は、店舗への来店や購入意欲を向上させる販売促進の手法のひとつでした。
基本的なアイテムは下記の7つをご紹介しました。
- のぼり旗
- ポスター
- バナースタンド
- タペストリー
- デジタルサイネージ
- ノベルティ
- パネル・等身大パネル・POP
店頭販促を成功させるポイントは、商品をわかりやすくディスプレイして明確なデザインで訴求し、キャンペーンなどのメリットを連動させることです。
そして、ぜひ効果測定を行って自分の店舗に合った店頭販促を見極めてください。
また、店頭販促の設置には顧客の導線を意識し、販促品の破損や情報の更新を忘れないように注意しましょう。
店頭販促でより良い店舗運営ができるよう、ぜひ有効に活用してみてください。
|ブログ一覧に戻る|
関連記事
2025.01.28
最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!
2024.08.06
【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性
2023.07.13
トロマット生地とは?特徴やおすすめの使い方を教えます!
関連記事
2025.01.28
最新鋭機 VUTEk Q5r 導入レポート!
2024.08.06
【インタビュー】現代アートにおけるインクジェット印刷の可能性
2023.07.13